普段何気なく飲んでいるコーヒーや烏龍茶。あの独特の「渋み」が好きという方もいれば、少し苦手という方もいるかもしれません。その渋みの正体こそが、ポリフェノールの一種である「タンニン」です。実はこのタンニン、私たちの体にさまざまな影響を与えています。
この記事では、そもそもタンニンとは何かという基本から、コーヒーと烏龍茶のどちらに多く含まれているのか、そしてタンニンがもたらす嬉しい効果や、摂取する際に少し気をつけたい点まで、やさしく解説していきます。この記事を読めば、タンニンに関する疑問がすっきり解消し、毎日のコーヒータイムやティータイムをより一層楽しめるようになるでしょう。
そもそもタンニンとは?コーヒーや烏龍茶の渋みの正体

コーヒーや烏龍茶を飲んだ時に感じる特有の渋み、その正体が「タンニン」です。タンニンは植物界に広く存在する成分で、私たちの食生活に深く関わっています。ここでは、タンニンの基本的な情報や、なぜ渋みを感じるのか、そしてどのような食品に含まれているのかを詳しく見ていきましょう。
ポリフェノールの一種「タンニン」の基本
タンニンは、植物が光合成を行う際に生成される苦味や色素の成分である「ポリフェノール」の仲間です。 自然界には5,000種類以上のポリフェノールが存在すると言われており、タンニンはその中でも代表的なものの一つです。 タンニンという名前は、動物の皮をなめして腐敗しない丈夫な「革」に変える技術(tanning)に由来しており、古くからこのなめし剤として利用されてきました。
タンニンは大きく分けて「加水分解性タンニン」と「縮合型タンニン」の2種類があります。 加水分解性タンニンは水に溶けやすく、柿やアーモンドなどに含まれています。 一方、縮合型タンニンは水に溶けにくく、お茶に含まれるカテキンが複数結合してできたもので、ぶどうの皮や紅茶などに含まれています。 このように、タンニンは一つの物質ではなく、様々な構造を持つ化合物の総称なのです。
タンニンがもたらす「渋み」のメカニズム
タンニンを口に含んだ時に強い渋みを感じるのは、「収れん作用」という働きによるものです。 収れん作用とは、タンパク質と結合して組織や血管を縮める作用のことです。 口の中に入ったタンニンが、舌や口の粘膜の表面にあるタンパク質と結合し、粘膜を変性させることで「渋い」という感覚を引き起こします。
この収れん作用は、肌につけることで毛穴を引き締める効果があるため、多くの化粧品にも応用されています。 また、植物にとってタンニンは、動物や昆虫に食べられないようにするための防御物質としての役割も担っています。未熟な果実が渋いのは、このタンニンの働きによるものです。
タンニンが含まれる代表的な飲み物・食べ物
タンニンは私たちの身の回りの多くの植物性食品に含まれています。
・果物:柿(特に渋柿)、ぶどう、いちご、クランベリー、ブルーベリー、りんごなど
・その他:カカオ、ナッツ類、豆類、栗の皮など
特に、赤ワインはその製造過程でぶどうの果皮や種子も一緒に漬け込むため、タンニンの渋みや風味が強く感じられる代表的な飲み物です。 お茶に含まれるタンニンの多くはカテキン類であり、ほぼ同義として扱われることもあります。 このように、タンニンは意識せずとも多くの食品から摂取している身近な成分なのです。
タンニン含有量比較!コーヒー vs 烏龍茶

コーヒーと烏龍茶、どちらも日常的によく飲まれる人気の飲み物ですが、渋みの成分であるタンニンはどちらに多く含まれているのでしょうか。ここでは、それぞれのタンニン含有量について、具体的なデータをもとに比較し、他の飲み物との違いも見ていきましょう。
コーヒーに含まれるタンニンの量
コーヒーの渋みや苦味の元となる成分もタンニンの一種です。 一般的に、コーヒー抽出液100mlあたりに含まれるタンニンの量は、約60mg~250mgとされています。 ただし、この量はコーヒー豆の種類や焙煎度合い、そして抽出方法によって大きく変動します。
コーヒーに含まれるポリフェノールの代表的なものに「クロロゲン酸」があります。 このクロロゲン酸も広い意味ではタンニンの一種とされ、コーヒーの渋みに関わっています。 浅煎りのコーヒー豆の方がクロロゲン酸は多く含まれており、焙煎が深くなるにつれて減少する傾向があります。 したがって、一般的に深煎りの苦いコーヒーよりも、浅煎りの酸味が特徴のコーヒーの方がタンニンの影響を受けやすいと考えることができます。
烏龍茶に含まれるタンニンの量
烏龍茶は、茶葉を発酵させる過程が緑茶と紅茶の中間にあたる「半発酵茶」です。 この発酵の過程で、緑茶の渋み成分であるカテキンが酸化・重合して、「ウーロン茶重合ポリフェノール」という烏龍茶特有のポリフェノールが生成されます。 これもタンニンの一種です。
文部科学省のデータによると、標準的な淹れ方をした烏龍茶100mlあたりのタンニン含有量は約30mgです。 これは、茶葉15gを90℃のお湯650mlで30秒間抽出した場合の数値であり、抽出時間や茶葉の量によって変動します。 緑茶のカテキンが酸化して別の物質に変化するため、緑茶に比べると渋みがまろやかになるのが特徴です。
結果発表!タンニンが多いのはどっち?
これまでのデータをもとに、一般的な抽出液100mlで比較すると、以下のようになります。
・コーヒー:約60mg~250mg
・烏龍茶:約30mg
この数値から、一般的な飲み方をした場合、コーヒーの方が烏龍茶よりもタンニンの含有量が多い傾向にあると言えます。 もちろん、これはあくまで目安であり、コーヒーの淹れ方(粉の量や抽出時間)や烏龍茶の淹れ方(茶葉の量や蒸らし時間)によっては、この関係が逆転する可能性も十分に考えられます。
他の飲み物(緑茶、紅茶など)との比較
参考までに、他のお茶とタンニンの量を比較してみましょう。抽出条件によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。(抽出液100mlあたり)
・玉露:約230mg
・紅茶:約100mg
・煎茶:約70mg
・ほうじ茶:約20mg
(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)を基にしたデータ)
この比較を見ると、玉露やコーヒーはタンニンが非常に多く、紅茶、煎茶、烏龍茶と続きます。 ほうじ茶や番茶は、高温で焙煎する過程でタンニン(カテキン)が減少するため、含有量が少ないのが特徴です。 渋みが苦手な方や、タンニンの摂取を控えたい場合は、ほうじ茶や麦茶(タンニン含有量ゼロ)などを選ぶと良いでしょう。
コーヒーや烏龍茶のタンニンがもたらす健康効果
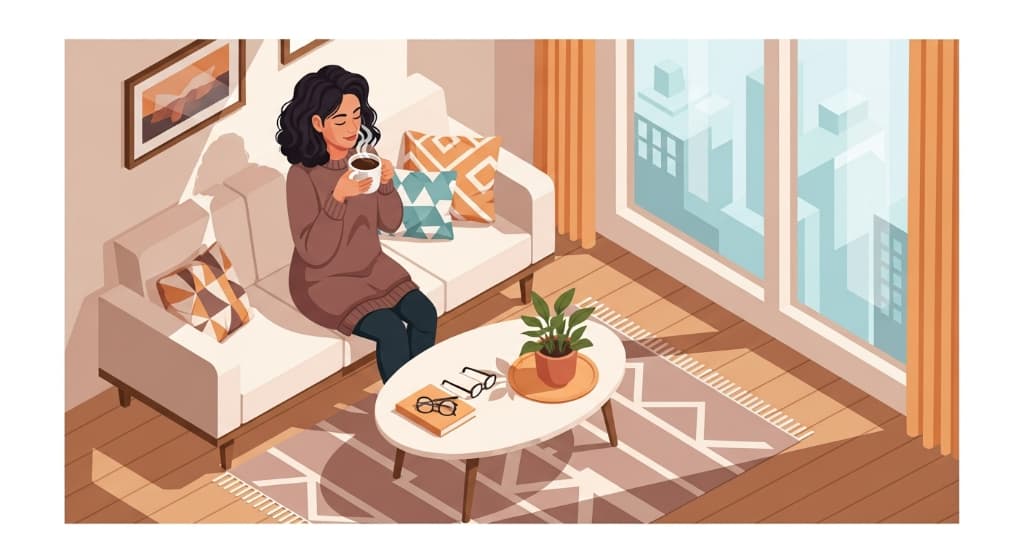
渋みの成分として知られるタンニンですが、実は私たちの健康に良い影響をもたらす様々な効果も期待されています。ポリフェノールの一種であるタンニンが持つ、アンチエイジングから生活習慣病予防、さらにはオーラルケアまで、その嬉しい働きについて詳しく見ていきましょう。
アンチエイジングに?タンニンの抗酸化作用
私たちの体は、呼吸によって取り込んだ酸素の一部から「活性酸素」を生成します。この活性酸素は、増えすぎると細胞を傷つけ、老化や免疫機能の低下、さらにはさまざまな病気の原因となります。 タンニンには、この活性酸素の働きを抑えたり、取り除いたりする強力な「抗酸化作用」があります。
この抗酸化作用により、細胞の老化を防ぐ効果が期待できるため、タンニンはアンチエイジングの観点からも注目されています。 日常的にコーヒーや烏龍茶を飲むことでタンニンを摂取することは、肌のハリを保ったり、シワを予防したりといった美容面での効果にも繋がる可能性があります。
生活習慣が気になる方に!コレステロール吸収を抑える働き
タンニンの抗酸化作用は、血液中の悪玉(LDL)コレステロールが酸化するのを防ぐ働きもあります。 悪玉コレステロールが酸化すると、血管の壁に付着して動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な生活習慣病のリスクを高めます。タンニンを摂取することで、この酸化を防ぎ、動脈硬化の予防に役立つと期待されています。
さらに、柿に含まれるタンニンには、炭水化物を摂取した後の血糖値の上昇を緩やかにする作用も報告されています。 また、お茶に含まれるカテキン(タンニンの一種)にも血糖値上昇抑制作用があることが知られています。 食事と一緒に、あるいは食後にコーヒーや烏龍茶を飲む習慣は、健康維持の一助となるかもしれません。
口臭予防にも?タンニンの抗菌・消臭効果
タンニンには、細菌の増殖を抑制する「抗菌作用」や、ウイルスを不活化させる「抗ウイルス作用」もあります。 この働きは、食中毒の原因菌や口の中の細菌に対しても効果的です。
口臭の主な原因の一つは、口の中にいる細菌がタンパク質を分解する際に発生するガスです。タンニンが持つ抗菌作用によって、これらの細菌の増殖を抑えることができるため、口臭予防効果が期待できます。 また、お茶でうがいをすると風邪予防になると言われるのも、このタンニン(カテキン)の抗菌・抗ウイルス作用によるものと考えられています。毎日のコーヒーや烏龍茶が、お口の健康を守る手助けをしてくれるかもしれません。
コーヒーや烏龍茶のタンニン、摂りすぎの注意点

多くの健康効果が期待できるタンニンですが、どんな食品でも言えるように、摂りすぎには注意が必要です。特に、鉄分の吸収を妨げる性質や、胃への負担などが指摘されています。ここでは、タンニンを摂取する際に知っておきたいデメリットや注意点を解説します。
鉄分の吸収を妨げる可能性
タンニンの最も注意すべき点として、鉄分の吸収を阻害する作用が挙げられます。 食物に含まれる鉄分には、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と、野菜や豆類に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります。タンニンは、特にこの「非ヘム鉄」と強く結合し、水に溶けにくい物質を作ってしまいます。 これにより、体が鉄分を吸収しにくくなるのです。
そのため、貧血気味の方や、月経などで鉄分が不足しがちな女性、成長期の子どもなどは、タンニンの摂り方に注意が必要です。 特に、鉄分を多く含む食事や、鉄剤のサプリメントを摂取する際は、コーヒーやお茶を飲むタイミングをずらすなどの工夫が推奨されます。
胃への負担と便秘のリスク
タンニンには、粘膜のタンパク質と結合して組織を引き締める「収れん作用」があります。 この作用が胃の粘膜に働くと、人によっては胃を荒らしてしまったり、消化不良を起こして吐き気や胃痛の原因になったりすることがあります。 特に空腹時に濃いコーヒーやお茶を飲むと、胃への刺激が強くなるため注意が必要です。
また、この収れん作用が腸に働くと、腸の動き(ぜん動運動)を抑制してしまうことがあります。 適量であれば下痢を改善する効果も期待できますが、摂りすぎてしまうと逆に腸の働きを抑えすぎてしまい、便秘を引き起こす可能性も指摘されています。 元々便秘に悩んでいる方は、タンニンの多い飲み物の摂取量に気をつけた方が良いかもしれません。
タンニン摂取、1日の適量は?
現在のところ、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」において、タンニンの明確な摂取目安量は設定されていません。 通常の食生活を送っていれば、タンニンが欠乏する心配はほとんどありませんが、過剰摂取による不調のリスクは知っておく必要があります。
具体的な数値を挙げるのは難しいですが、例えば緑茶であれば1日に1〜2杯程度が適量という意見もあります。 コーヒーや烏龍茶についても、常識の範囲内で楽しむ分には大きな問題はないと考えられます。自分の体調と相談しながら、一日に何杯も飲みすぎないように心がけることが大切です。もし胃の不快感や便秘などの症状が出るようであれば、少し量を減らしてみると良いでしょう。
タンニンと上手に付き合う!コーヒー・烏龍茶の飲み方の工夫

タンニンのメリットは活かしつつ、デメリットは上手に避けたいものです。ここでは、日々の生活の中で少し意識するだけでできる、コーヒーや烏龍茶の飲み方の工夫をご紹介します。自分の体質やライフスタイルに合わせて取り入れてみましょう。
貧血気味の人は食事中の摂取を避ける
タンニンが鉄分の吸収を妨げる影響を最も受けやすいのは、食事中や食後すぐです。 貧血の診断を受けている方や、鉄分不足が気になる方は、食事と一緒にコーヒーや烏龍茶を飲むのは避けた方が賢明です。
食事から鉄分をしっかり吸収させるためには、食中・食後の飲み物はタンニンを含まない麦茶やほうじ茶、水などに切り替えるのがおすすめです。 コーヒーや烏龍茶を楽しみたい場合は、食事と食事の間、例えば食後1〜2時間ほど時間を空けてから飲むようにすると、鉄分の吸収への影響を最小限に抑えることができます。
空腹時を避けて胃への負担を軽減
タンニンやカフェインは、空腹時に摂取すると胃の粘膜を直接刺激し、胃痛や胸やけの原因となることがあります。 特に胃が弱いと感じる方は、朝起きてすぐや、食事を抜いた後などの空腹時に濃いコーヒーやお茶を飲むのは避けましょう。
コーヒーや烏龍茶を飲むなら、食後がおすすめです。 食べ物が胃の中にある状態であれば、胃酸が中和され、胃粘膜への直接的な刺激を和らげることができます。また、何か少しお菓子などをつまみながら飲むのも良い方法です。自分の胃の調子をみながら、飲むタイミングを工夫してみてください。
牛乳や豆乳を加えるのもおすすめ
コーヒーや紅茶に牛乳を入れると、味がまろやかになりますが、これは牛乳に含まれるタンパク質「カゼイン」がタンニンと結合するためです。タンニンがカゼインと結びつくことで、舌や胃の粘膜への刺激が緩和されます。
コーヒーであればカフェオレやカフェラテに、紅茶であればミルクティーにするのがおすすめです。この方法は、タンニンの渋みが苦手な方にも適しています。また、二日酔いで胃が弱っている時にコーヒーを飲む場合も、ミルクを入れると刺激が和らぐとされています。 牛乳が苦手な方は、豆乳でも同様の効果が期待できます。
抽出時間や温度でタンニンの量をコントロール
タンニンは、お湯の温度が高いほど、また抽出時間が長いほど、多く溶け出す性質があります。 この性質を利用すれば、自分でタンニンの量をある程度コントロールすることが可能です。
タンニンの摂取量を抑えたい場合は、コーヒーであれば抽出時間を短めにしたり、水出しコーヒーを選んだりする方法があります。水出しコーヒーは低温でじっくり抽出するため、タンニンやカフェインの溶出が抑えられ、すっきりとまろやかな味わいになります。お茶の場合も、少し低めの温度のお湯で淹れたり、蒸らし時間を短くしたりすることで、渋みを抑えることができます。
まとめ:タンニンを知ってコーヒー・烏龍茶をもっと楽しもう

この記事では、「タンニン」をキーワードに、コーヒーと烏龍茶にまつわる様々な情報をお届けしました。
渋みの正体であるタンニンは、植物由来のポリフェノールの一種です。 一般的に、コーヒーの方が烏龍茶よりもタンニンの含有量が多い傾向にありますが、これは豆の種類や淹れ方によっても変わります。
タンニンには、老化の原因となる活性酸素を抑える「抗酸化作用」や、コレステロールの酸化を防ぐ働き、口臭を予防する抗菌作用など、健康に役立つ嬉しい効果がたくさんあります。
その一方で、鉄分の吸収を妨げたり、胃に負担をかけたりする可能性もあるため、摂りすぎには注意が必要です。 特に貧血気味の方は、食事と時間をずらして飲む、牛乳を加える、抽出時間を短くするといった工夫を取り入れると良いでしょう。
タンニンの良い面と注意すべき点を理解することで、私たちはもっと賢くコーヒーや烏龍茶と付き合っていくことができます。ご自身の体調やライフスタイルに合わせて飲み方を工夫し、毎日のリラックスタイムをより豊かに楽しんでください。




コメント