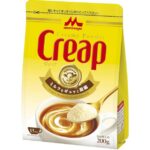コーヒーや紅茶にまろやかなコクを加えてくれる「マリーム」。長年多くの家庭で愛用されている一方、「マリームは体に悪い」という噂を耳にして、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。毎日使うものだからこそ、その安全性は気になりますよね。
この記事では、「マリームは体に悪い」というキーワードで検索されている方に向けて、マリームの原材料や含まれる添加物、そしてそれらが体に与える影響について、専門的な内容も分かりやすく解説していきます。植物性油脂の正体や、トランス脂肪酸のリスク、添加物の安全性など、気になるポイントを一つひとつ丁寧に見ていきましょう。この記事を読めば、マリームと上手に付き合っていくための知識が身につき、安心して毎日のコーヒータイムを楽しめるようになるはずです。
マリームが体に悪いと言われる主な理由

多くの人に親しまれているマリームですが、なぜ「体に悪い」というイメージが持たれるのでしょうか。その背景には、主に3つの理由が考えられます。原材料の構成、特定の脂肪酸の存在、そして食品添加物の使用です。ここでは、多くの人が懸念しているポイントを一つずつ掘り下げていきます。
原材料の大部分が「植物性油脂」であること
マリームの主原料の一つは植物性油脂です。一般的に「植物性」と聞くと、健康的なイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、マリームに使用されている植物性油脂は、常温で固体の「硬化油」と呼ばれるものです。
これは、液体の植物油に水素を添加して人工的に固めたもので、この過程でトランス脂肪酸が生成される可能性があります。また、どの植物から採れた油なのかが具体的に表示されていないため、消費者がその内容を詳しく知ることが難しい点も、不安を感じさせる一因となっています。さらに、油脂であるため、摂りすぎはカロリー過多につながる可能性も指摘されています。ミルクの代用品として使われることが多いですが、その成分は牛乳とは大きく異なるため、同じ感覚で大量に使うことには注意が必要です。
「トランス脂肪酸」が含まれているという懸念
マリームが体に悪いと言われる最大の理由の一つが、トランス脂肪酸の存在です。トランス脂肪酸は、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を増加させ、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を減少させる働きがあることが知られています。
これにより、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や狭心症などの心臓疾患のリスクを高める可能性が指摘されています。世界保健機関(WHO)はトランス脂肪酸の摂取量を総エネルギー摂取量の1%未満に抑えるよう勧告しており、海外では表示義務化や使用禁止などの厳しい規制が敷かれている国も少なくありません。マリームの製造過程でトランス脂肪酸が生成される可能性があることから、「体に悪い」というイメージに繋がっているのです。
「添加物」が使用されていることへの不安
マリームには、品質を安定させ、風味を良くするために、乳化剤、カラメル色素、香料などの食品添加物が使用されています。日本の食品衛生法で安全性が確認され、使用が認められているものばかりですが、「添加物」という言葉そのものに、漠然とした不安を感じる人も少なくありません。例えば、乳化剤は水と油を均一に混ぜ合わせるために不可欠な成分ですが、その種類や摂取量によっては腸内環境に影響を与える可能性を指摘する声もあります。
また、カラメル色素や香料についても、その製造方法や由来が気になるという意見が見られます。これらの添加物が複合的に体に与える影響については、まだ解明されていない部分も多く、健康志向の高まりとともに、添加物を避けたいと考える人が増えていることも、「マリームは体に悪い」という認識に影響していると考えられます。
マリームの原材料を徹底チェック!体に悪い成分は入っている?

「マリームは体に悪い」という噂の真相を探るため、まずはパッケージに記載されている原材料を一つひとつ見ていきましょう。どのようなものが使われていて、それぞれがどんな役割を果たしているのかを知ることで、安全性について正しく理解することができます。
主成分「水あめ」と「植物性油脂」の正体
マリームの原材料表示を見ると、最も多く含まれているのが「水あめ」と「植物性油脂」です。水あめは、でんぷんを糖化させて作られる甘味料で、マリームに穏やかな甘みとコクを与え、粉末が固まるのを防ぐ役割も担っています。
主成分は糖質なので、摂りすぎは血糖値の上昇やカロリー過多につながる可能性があります。次に多い植物性油脂は、製品にクリーミーな口当たりと濃厚さを与えるための重要な成分です。しかし、前述の通り、これは液体の油を固形状にした「硬化油」であり、この加工工程でトランス脂肪酸が生成される可能性があります。また、「植物性油脂」とだけ表示されているため、パーム油、大豆油、なたね油など、どの種類の油が使われているのか消費者には分かりません。それぞれの油で脂肪酸の組成も異なるため、詳細な情報が開示されていない点に不安を感じる人もいるでしょう。
乳たん白と乳化剤の役割
マリームには「乳たん白」も含まれています。これは牛乳からカゼインというたんぱく質を抽出したもので、製品に乳製品らしい風味とコクを加える役割があります。乳製品アレルギーの原因となる成分ですので、アレルギーのある方は注意が必要です。そして、水と油という本来混ざり合わないものを均一に混ぜ合わせるために不可欠なのが「乳化剤」です。
マリームにおいては、お湯やコーヒーに溶かした際に、油脂が分離せずに均一な状態を保つために使われています。乳化剤には様々な種類があり、マリームに使用されているものは食品衛生法に基づき安全性が確認されています。しかし、一部の研究では、特定の乳化剤の過剰摂取が腸内環境のバランスを崩す可能性も示唆されており、添加物を気にする方にとっては懸念材料の一つとなるかもしれません。
気になる添加物「カラメル色素」と「香料」の安全性
マリームの茶色がかった色は「カラメル色素」によるものです。カラメル色素は、糖類を加熱して作られる着色料で、製品に美味しそうな色合いと香ばしい風味を与えます。カラメル色素には4つの製法があり、一部の製法で作られるものには、製造過程で副産物(4-メチルイミダゾールなど)が生成される可能性があります。
これについては発がん性の懸念が指摘されたこともありますが、日本で使用が認められているものは、安全な量に基準値が定められています。通常の使用量であれば健康へのリスクは極めて低いと考えられています。また、マリーム特有の甘くクリーミーな香りは「香料」によって付けられています。香料も多種多様な物質の組み合わせで作られていますが、使用されるものはすべて安全性が確認されています。しかし、化学的に合成された香料に対して抵抗を感じる人もおり、自然な風味を好む方にとっては避けたい成分かもしれません。
リン酸塩(Na、K)とは?
原材料表示にある「pH調整剤」や「安定剤」として使われるのが「リン酸塩(Na、K)」です。リン酸塩は、品質を安定させ、滑らかな口当たりを保つために添加されます。リンは体に必要なミネラルですが、加工食品から過剰に摂取すると、カルシウムの吸収を妨げたり、腎臓に負担をかけたりする可能性が指摘されています。
特に腎機能が低下している方は注意が必要です。リンは肉や魚、乳製品など多くの食品に自然に含まれているため、マリームだけでなく、他の加工食品の摂取量にも気を配り、全体としてリンの摂取量が過剰にならないように意識することが大切です。とはいえ、マリームをコーヒーに少量加える程度であれば、リン酸塩の摂取量が健康に影響を及ぼす心配はほとんどないと言えるでしょう。
マリームに含まれるトランス脂肪酸は体に悪い?

マリームが体に悪いと言われる最大の要因である「トランス脂肪酸」。この成分について正しく理解することが、マリームとの付き合い方を考える上で非常に重要です。ここでは、トランス脂肪酸の基本的な知識から、マリームへの含有量、国内外の規制状況まで詳しく見ていきましょう。
トランス脂肪酸とは?なぜ体に悪いと言われるのか
トランス脂肪酸は、油脂に含まれる不飽和脂肪酸の一種です。構造の違いによって「トランス型」と「シス型」に分けられます。天然の植物油に含まれる不飽和脂肪酸のほとんどはシス型です。一方、トランス脂肪酸は、液体の植物油に水素を添加して固形や半固形の油脂(硬化油)を製造する過程で主に生成されます。
マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング、そしてそれらを原料とするパン、ケーキ、揚げ物などに含まれています。また、牛などの反芻動物の胃の中で微生物によっても作られるため、牛肉や乳製品にも微量に含まれています。このトランス脂肪酸が問題視されるのは、健康への悪影響が科学的に明らかになっているためです。具体的には、血液中の悪玉(LDL)コレステロールを増やし、善玉(HDL)コレステロールを減らす作用があります。これにより、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や狭心症といった冠動脈疾患のリスクを高めることが確実視されています。
マリームに含まれるトランス脂肪酸の量
では、実際にマリームにはどれくらいのトランス脂肪酸が含まれているのでしょうか。製造元であるAGF(味の素AGF)の公式ウェブサイトによると、マリーム1杯分(3g)あたりのトランス脂肪酸含有量は約0.03gであると公表されています。
これは、世界保健機関(WHO)が推奨する1日のトランス脂肪酸摂取量の目標値(総エネルギー摂取量の1%未満)に照らし合わせると、非常に少ない量です。例えば、1日の摂取カロリーが2000kcalの場合、トランス脂肪酸の摂取目標量は2g未満となります。マリームを1日に数杯飲む程度では、この目標値を大幅に超える心配は低いと言えるでしょう。メーカー側も、消費者の健康志向の高まりを受け、製造工程の見直しなどを通じてトランス脂肪酸の低減に努めています。
日本と海外のトランス脂肪酸に対する規制の違い
トランス脂肪酸に対する規制は、国によって大きく異なります。アメリカでは、2018年に加工食品への部分水素添加油(トランス脂肪酸の主な原因)の使用が原則禁止されました。また、カナダ、スイス、デンマークなどでも同様の規制が導入されています。多くの国で、食品中のトランス脂肪酸含有量の表示が義務付けられています。
一方、日本では、トランス脂肪酸の表示義務や使用規制はありません。これは、日本人の平均的なトランス脂肪酸摂取量が、WHOの目標値である総エネルギー比1%未満を下回る0.3%程度と推定されており、健康への影響は小さいと評価されているためです。しかし、食生活の欧米化に伴い、脂質の摂取量は年々増加傾向にあります。特に、パンや洋菓子、揚げ物などを好んで食べる人は、意識しないうちにトランス脂肪酸を過剰に摂取している可能性もあるため、注意が必要です。
日常生活でトランス脂肪酸を避けるためのポイント
マリームに含まれるトランス脂肪酸は少量ですが、健康のためには日々の食生活全体で摂取量を意識することが大切です。トランス脂肪酸を多く含む可能性があるのは、マーガリン、ファットスプレッド、ショートニングを使用した加工食品です。具体的には、菓子パン、ケーキ、クッキー、スナック菓子、ドーナツ、フライドポテトなどが挙げられます。
これらの食品を食べる頻度や量を見直すことが、トランス脂肪酸の摂取量を減らすための第一歩です。食品を選ぶ際には、原材料表示を確認し、「ショートニング」「マーガリン」「加工油脂」などの記載がある場合は、トランス脂肪酸が含まれている可能性があると認識しておきましょう。バランスの取れた和食中心の食生活を心がけることも、結果的にトランス脂肪酸の摂取を抑えることに繋がります。
マリームと他の選択肢との比較

コーヒーや紅茶の風味を豊かにするものは、マリームだけではありません。牛乳や生クリーム、他のメーカーのクリーミングパウダーなど、様々な選択肢があります。それぞれの特徴を知り、自分の好みや健康への意識に合わせて使い分けるのも一つの方法です。
牛乳や生クリームとの違い
最も大きな違いは、主成分です。マリームの主成分が植物性油脂と糖質であるのに対し、牛乳や生クリームは動物性の乳脂肪と乳たんぱく質が主成分です。そのため、風味や栄養価が大きく異なります。牛乳はカルシウムやたんぱく質が豊富で、自然な甘みとさっぱりとしたコクが特徴です。生クリームは乳脂肪分が高く、非常に濃厚でクリーミーな味わいになりますが、その分カロリーも高くなります。
一方、マリームは植物性油脂ならではの軽い口当たりと、香料による甘い香りが特徴です。また、マリームは常温で長期間保存できる粉末タイプであるのに対し、牛乳や生クリームは冷蔵保存が必要で賞味期限も短いという利便性の違いもあります。栄養面を重視するなら牛乳、濃厚さを求めるなら生クリーム、手軽さや独特の風味を好むならマリーム、といった使い分けができるでしょう。
他のコーヒーフレッシュ(ポーションタイプ)との比較
喫茶店やコンビニでよく見かける、小さなポーション容器に入ったコーヒーフレッシュ(コーヒー用クリーム)も、マリームと同様に植物性油脂を主原料として作られているものがほとんどです。原材料は、植物性油脂、砂糖、乳化剤、安定剤、香料、カラメル色素などで構成されており、マリームの成分と非常によく似ています。
液体であるため、粉末のマリームよりも溶けやすいというメリットがあります。ただし、こちらも製品によってはトランス脂肪酸が含まれている可能性があります。また、ポーションタイプは使い切りで衛生的ですが、一つあたりの量が決まっているため、量の調整がしにくいと感じる場合もあるかもしれません。保存性に関しても、未開封であれば常温で保存できるものが多く、利便性は高いと言えます。風味や口当たりは製品によって微妙に異なるため、いくつか試してみて好みのものを見つけるのも良いでしょう。
「ブライト」や「クリープ」との違いは?
マリームと同じ粉末タイプのクリーミングパウダーとして、ネスレの「ブライト」や森永乳業の「クリープ」がよく知られています。「ブライト」の主原料はコーンシロップ(水あめ)と植物性油脂で、マリームと非常に似た構成です。
そのため、風味や使い勝手も似ており、植物性油脂を主原料とするクリーミングパウダーの代表的な選択肢と言えます。一方、「クリープ」は他の2製品とは大きく異なり、主原料が「乳製品(乳糖、乳たんぱく)」です。植物性油脂を使用せず、牛乳の成分をギュッと凝縮して作られているのが最大の特徴です。そのため、牛乳に近い自然なコクと風味を味わうことができます。価格はマリームやブライトに比べて高めですが、原材料にこだわりたい方や、よりミルク感の強い味わいを好む方に選ばれています。ただし、乳製品が主原料なので、乳アレルギーの方は使用できません。
マリームを安心して楽しむためのQ&A

マリームについて様々な角度から見てきましたが、ここではさらに具体的な疑問にお答えしていきます。一日の適量や、使用を控えた方が良いケースなど、日々の生活で気になるポイントをQ&A形式で解説します。
マリームの1日の適量は?
マリームには、明確に「1日何杯まで」という基準が定められているわけではありません。しかし、その主成分が糖質と脂質であることを考えると、摂りすぎには注意が必要です。ティースプーン1杯(約3g)あたりのカロリーは約16kcal、糖質(炭水化物)は約1.8gです。コーヒー1杯にスプーン2杯入れるとすると、それだけで約32kcalになります。
これを1日に何杯も飲むと、知らず知らずのうちにカロリーや糖質の過剰摂取につながる可能性があります。特に、血糖値が気になる方や、ダイエット中の方は注意が必要です。前述の通り、トランス脂肪酸の含有量はごく微量なので、その点では過度に心配する必要はありません。しかし、バランスの取れた食生活全体を考えるならば、1日に1〜2杯程度を目安に、楽しみとして味わうのが賢明な付き合い方と言えるでしょう。
マリームを避けたほうが良い人はいる?
ほとんどの人にとっては、適量の摂取であれば問題ありませんが、特定の持病がある方やアレルギー体質の方は注意が必要です。まず、原材料に「乳たん白」が含まれているため、牛乳アレルギーの方は使用を避けるべきです。アナフィラキシーショックなどの重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があります。
また、主成分が糖質であるため、糖尿病の方や血糖値のコントロールが必要な方は、摂取量に注意するか、使用前にかかりつけの医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。さらに、腎臓の機能が低下している方は、添加物として含まれる「リン酸塩」の摂取に注意が必要です。リンの排泄がうまくできず、体に負担をかける可能性があるためです。これらに該当しない健康な方であっても、特定の成分に不安を感じる場合は、無理して使用する必要はありません。
マリームのメリットとデメリットのまとめ
ここで、マリームのメリットとデメリットを整理してみましょう。
・常温で長期間保存でき、使いたい時にさっと使える利便性
・牛乳や生クリームに比べて安価であること
・コーヒーや紅茶の風味を邪魔しすぎず、まろやかなコクを加えることができる
・お菓子作りや料理にも活用できる汎用性の高さ
・主成分が植物性油脂と糖質であり、栄養価は牛乳に劣る
・摂りすぎはカロリーや糖質の過剰摂取につながる
・製造過程でトランス脂肪酸が微量に生成される
・乳化剤や香料、着色料などの食品添加物が使用されている
・牛乳アレルギーの人は使用できない
これらの点を総合的に理解した上で、自分のライフスタイルや価値観に合わせて、マリームを利用するかどうかを判断することが大切です。
まとめ:マリームは体に悪い?正しく知って上手な使い方を

この記事では、「マリームは体に悪い」という疑問について、その原材料や成分、健康への影響などを詳しく解説してきました。
マリームが体に悪いと言われる背景には、主成分である「植物性油脂」、それに伴う「トランス脂肪酸」の懸念、そして「食品添加物」への不安があることが分かりました。しかし、一つひとつの成分を詳しく見ていくと、AGFが公表している情報によれば、マリームに含まれるトランス脂肪酸はごく微量です。また、使用されている添加物も、日本の食品衛生法で安全性が認められたものです。
ただし、主成分が糖質と脂質であるため、カロリーや糖質の摂りすぎには注意が必要です。牛乳とは成分が大きく異なるため、栄養を補う目的での使用には適していません。
結論として、マリームが「体に悪い」と一概に断定することはできません。どんな食品でも、そればかりを過剰に摂取すれば健康を害するリスクはあります。マリームの特性を正しく理解し、1日に1〜2杯程度を楽しむ範囲であれば、過度に心配する必要はないでしょう。利便性や風味の好み、そしてご自身の健康状態を考慮しながら、上手にマリームと付き合っていくことが大切です。